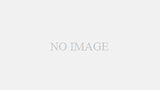東京下町ガイド の「神社」カテゴリーでは、東京の下町エリアにあるいろいろな神社や寺院をわかりやすく紹介しています。あなたの東京観光におすすめのスポットを毎回 1 つ取り上げます。
今回の記事では、台東区の浅草にある 浅草神社(あさくさ じんじゃ)を紹介します。
浅草神社のすぐ隣には、東京で一番古い寺院である 浅草寺(せんそうじ)があります。浅草神社と浅草寺は、もともと 1 つでした。そのため、この 2 つの社寺はとても深い繋がりがあります。
浅草神社は、三社権現(さんじゃ ごんげん)を祀っています。そのため、この神社を「三社さま」とも呼びます。なお、三社権現は、浅草寺の創建のきっかけとなった 3 人を神格化したものです。
浅草神社は、毎年 5 月に「三社祭(さんじゃ まつり)」という、例大祭を行います。三社祭は日本有数の規模を誇る祭です。2017 年の三社祭には 200 万人以上の人出がありました。
今回の記事では、浅草神社に関する以下の内容をやさしく解説します。
- 歴史
- 祀られている神さま
- 見どころ
- アクセス方法
- その他
この記事を読むことで、浅草神社についてより深く理解できます。浅草神社を訪れる際は、ぜひこの記事を参考にしてください。
由緒(歴史)
浅草神社によると、この神社の始まりは 7 世紀にまでさかのぼります。また、その歴史は、浅草神社の隣りにある 浅草寺(せんそうじ)と密接な関係があります。
7 世紀の初めごろ、檜前浜成(ひのくま はまなり)と 檜前武成(ひのくま たけなり)という、漁師の兄弟がいました。
628 年(推古 36 年)の 3 月 18 日、檜前兄弟は隅田川で漁をしていました。その際、彼らは投網の中に仏像を見つけたのです。しかし、檜前兄弟はその仏像が何なのかわかりませんでした。
檜前兄弟は、浅草の郷士(ごうし)である 土師真中知(はじ まなかち)にその仏像を見せました。その結果、この仏像は 聖観世音菩薩(しょう かんぜおん ぼさつ)であることがわかりました。
慈悲の仏さまである 観世音菩薩(かんぜおん ぼさつ)は、多くの人びとの苦しみや願いを聞くため、相手に応じていろいろな姿に変化(へんげ)するといわれています。聖観音菩薩は、観音菩薩が変化する前の姿です。
檜前兄弟と地元の人たちは簡素な仏堂を作り、そこに聖観世音菩薩の像を祀りました。
その後、土師真中知は出家し、自宅を寺院としました。そして、檜前兄弟が見つけた聖観世音菩薩の像を本尊としてその寺院に祀りました。これが浅草寺の始まりです。
平安時代の終わりから鎌倉時代の初めごろ、土師真中知の子孫は、聖観世音菩薩のお告げを受けました。そのお告げの主な内容は、以下のとおりです。
あなたたちの祖先は、私(聖観世音菩薩)を水中から救い出しました。さらには、彼らは私を浅草寺に祀りました。彼らの功績は称賛に値します。
だから、彼らを 三社権現(さんじゃ ごんげん)という神として浅草寺の隣に祀りなさい。そうすれば、あなたたちやこの地域はずっと繁栄するでしょう
土師真中知と檜前兄弟の子孫たちは、自分たちの先祖の 3 人を郷土神(その土地の守り神)として祀りました。これが浅草神社の始まりです。当時は、三社権現社(さんじゃ ごんげん しゃ)という名前でした。
なお、三社権現の「三」は「土師真中知と檜前兄弟の 3 人」、「社」は「その土地を守る神さま」、そして、「権現」は「神さまの尊号」です。
1868 年(明治元年)、明治政府は 神仏分離令(しんぶつ ぶんり れい)を発令しました。これは、神道と仏教、神さまと仏さま、そして神社と寺院を明確に区別する法律です。
同年、三社権現社は浅草寺から独立しました。その際、三社権現社は名前を 三社明神社(さんじゃ みょうじんしゃ)に変更しました。1873 年(明治 6 年)、三社明神社は、名前を浅草神社に変更しました。
祀られている神さまとご神徳(ご利益)
三社権現
浅草神社の主神(しゅしん)は、三社権現(さんじゃ ごんげん)です。主神とは、その神社で中心となる神さまのことです。
三社権現は浅草神社と浅草寺の始まりとなった、次の 3 人を 郷土神(きょうどしん)として祀ったものです。郷土伸とは、その土地の守り神のことです。氏神(うじがみ)ともいいます。
東照宮
浅草神社は、配神(はいしん)として 東照宮(とうしょうぐう)を祀っています。配神とは、主神と一緒に祀られている神さまを指します。
東照宮は、江戸幕府の初代将軍である 徳川家康(とくがわ いえやす)のことです。また、東照宮を 東照大権現(とうしょう だいごんげん)とも呼びます。
浅草神社によると、浅草神社が東照宮を祀るようになったのは 1649 年(慶安 2 年)のことです。
東照宮は、国家鎮護(こっか ちんご)の神さまです。国家鎮護とは、国を災いから守ることです。この神さまの主なご神徳(ご利益)は、次のとおりです。
- 仕事運上昇(しごとうん じょうしょう):仕事がうまくいく
- 商売繁盛(しょうばい はんじょう):商いがうまくいく
- 家内安全(かない あんぜん):家族が健康で安全に過ごせる
- 心願成就(しんがん じょうじゅ):神仏に強く願えば何でも叶う
- その他
大国主命
大国主命(おおくにぬし の みこと)も浅草神社の配神です。大国主命は、大己貴命(おおなむち の みこと)とも呼ばれます。
日本神話の物語「因幡の白兎」で、ウサギを助けた(治療のアドバイスを与えた)のが大国主命(当時の名前は大己貴命)です。そのため、大国主命は医薬の神さまとしてもみなされるようになりました。
大国主命は、国造り、医薬、そして、縁結びの神さまです。この神さまの主なご神徳(ご利益)は、次のとおりです。
- 商売繁盛(しょうばい はんじょう):商いがうまくいく
- 病気平癒(びょうき へいゆ):病気が治る
- 夫婦和合(ふうふ わごう):夫婦が仲良く暮らせる
- その他
恵比寿天
恵比寿天(えびすてん)も浅草神社の配神です。恵比寿天は、事代主神(ことしろぬし の かみ)と同一視されます。
恵比寿天は、漁業と商売の神さまです。この神さまの主なご神徳(ご利益)は、次のとおりです。
- 大漁追福(たいりょう ついふく):魚がたくさん穫れる
- 商売繁盛(しょうばい はんじょう):商いがうまくいく
- 家内安全(かない あんぜん):家族が健康で安全に過ごせる
- その他
倉稲魂命
浅草神社の境内社(けいだいしゃ)の 被官稲荷神社(ひかん いなり じんじゃ)は、倉稲魂命(うか の みたま の みこと)を祀っています。境内社とは、境内にある小さな神社のことです。
倉稲魂命は、穀物、農業、そして、芸能の神さまです。また、倉稲魂命は、同じく穀物をつかさどる神さまの 稲荷神(いなりしん)と同一視されます。
倉稲魂命の主なご神徳(ご利益)は、次のとおりです。
- 五穀豊穣(ごこく ほうじょう):農作物がたくさん穫れる
- 商売繁盛(しょうばい はんじょう):商いがうまくいく
- 家内安全(かない あんぜん):家族が健康で安全に過ごせる
- 芸事上達(げいごと じょうたつ):音楽、芸術、芸能などが上達する
- その他
木花開耶姫命
浅草神社の境外社(けいがいしゃ)の 浅草富士浅間神社(あさくさ ふじ せんげん じんじゃ)は、木花開耶姫命(このはな さくやひめ の みこと)を祀っています。
この神さまは、富士山を象徴する、とても美しい神さまです。桜の語源やかぐや姫のモデルとなったとわれています。
木花開耶姫命は、火と安産と子育ての神さまです。この神さまの主なご神徳(ご利益)は、次のとおりです。
- 火難除け(かなん よけ):火に関する災いを避けることができる
- 安産(あんざん):母子ともに健康に出産できる
- 子授け(こさずけ):子どもを授かることができる
- その他
見どころ
社殿
浅草神社の社殿は、1649 年(慶安 2 年)に江戸幕府の第三代将軍である徳川家光(とくがわ いえみつ)が建てたものです。
この社殿は、権現造り(ごんげん づくり)と呼ばれる建物です。その特徴は、本殿(神さまを祀るための建物)、幣殿(儀式を行うための建物)、および拝殿(参拝するための建物)が渡り廊下で繋がっていることです。権現造りは、江戸時代の初期の代表的な神社の建築様式です。
社殿の外壁は漆で塗装されており、さらに麒麟や飛龍などの霊獣が色鮮やかに描かれています。社殿は経年劣化が目立ってきていたため、1961 年(昭和 36 年)と 1994 年(平成 6 年)にそれぞれ 3 年かけて修営されています。
浅草神社の社殿は度重なる災害や戦争の被害を免れ、現在も当時の面影をそのままに残しています。そのため、1951 年(昭和 26 年)に国の重要文化財に指定されています。
三社祭
三社祭(さんじゃ まつり)は、毎年 5 月の第 3 週に行われる浅草神社の例大祭です。正式名称は浅草神社例大祭ですが、三社祭の名前で親しまれています。
浅草神社によると、三社祭が最初に行われたのは 1312 年(正和元年)とのことです。つまり、この祭りは 700 年以上の歴史があります。
三社祭では 3 日間に渡ってさまざまな行事が行なわれます。その中でも最大の見ものは神輿渡御です。神輿渡御とは、神輿を担いて練り歩くことです。100 基を超える神輿が練り歩く様はとても迫力があります。
三社祭の期間中は浅草一帯が 1 年でもっとも活気づくといわれています。ウィキペディアによると 200 万人を超える人出を数えるとのことです。
被官稲荷神社
被官稲荷神社(ひかん いなり じんじゃ)は、浅草神社の境内社(けいだいしゃ)です。つまり、この神社は、浅草神社の境内にあり、浅草神社が管理しています。
この神社は、浅草神社の本殿に向かって右側にあります。そのため、この神社は見逃されがちな場所にあるかもしれません。
被官稲荷神社の創建には、浅草の町火消の親分である 新門辰五郎(しんもん たつごろう)が深く関わっています。また、稲荷神社らしく、境内にはたくさんの愛らしい狐たちが祀られています。
被官稲荷神社の詳細については、次の記事を参照してください。
浅草富士浅間神社
浅草富士浅間神社(あさくさ ふじ せんげん じんじゃ)は、浅草神社の境外社(けいがいしゃ)です。この神社は、浅草神社から徒歩 5 分ほど離れた場所にありますが、浅草神社が管理しています。
浅草富士浅間神社は、富士山を象徴する神さまである、木花開耶姫命(このはな さくやひめ の みこと)を祀っています。そのため、この神社を お富士さん と呼ぶこともあります。なお、この神さまの名前は桜の語源となったといわれています。
浅草富士浅間神社の例大祭に関連して、お富士さんの植木市 が 5 月と 6 月の最終土曜日と日曜日に開かれます。長國寺(ちょうこくじ)の あじさい祭り と並び、この植木市は浅草の初夏の風物詩です。
浅草富士浅間神社の詳細については、次の記事を参照してください。
浅草名所七福神(恵比寿天)
浅草神社の恵比寿天は、浅草名所七福神(あさくさ などころ しちふくじん)の 1 柱(はしら)に数えられています。浅草名所七福神とは、東京都の台東区と荒川区にある 9 つの社寺に祀られている七福神のことです。
浅草名所七福神めぐりは、おすすめの浅草観光の 1 つです。通常、七福神めぐりは正月に行いますが、浅草名所七福神めぐりはいつでも楽しむことができます。
浅草名所七福神の詳細については、次の記事を参照してください。
浅草廿日戎
浅草神社の 浅草廿日戎(あさくさ はつか えびす)は、その年の最初の恵比寿天の縁日です。この日に恵比寿天をお参りすると、特にご利益があるといわれています。
浅草神社は、浅草廿日戎を毎年 1 月 19 日と 20 日の 2 日間にわたって開催します。これは、関東では 1 月 20 日がその年最初の恵比寿天の縁日とされているためです。浅草廿日戎の名前もこの縁日(20 日)に由来します。
浅草廿日戎の詳細については、次の記事を参照してください。
各種情報
社務所の受付時間
- 午前 9 時から午後 4 時まで
電話番号
- 03-3844-1575
住所
- 〒111-0032 東京都 台東区 浅草 2-3-1
地図
アクセス(めぐりんバス)
- 北めぐりん(浅草まわり)の 浅草寺北 停留所(停留所の番号:22 番)から徒歩 2 分
- 北めぐりん(浅草まわり)の 二天門 停留所(停留所の番号:23 番)から徒歩 2 分
- 東西めぐりんの 雷門通り 停留所(停留所の番号:31 番)から徒歩 7 分
- 東西めぐりんの 雷門前 停留所(停留所の番号:33 番)から徒歩 7 分
- ぐるーりめぐりんの 浅草雷門 停留所(停留所の番号:17-2 番)から徒歩 7 分
めぐりんバスは台東区のコミュニティ バスです。台東区を観光する場合、めぐりんバスはとても便利です。めぐりんバスの詳細については、次の記事を参照してください。
アクセス(都営バス)
- 都営バス(草 43)の 浅草雷門 停留所 から徒歩 5 分
- 都営バス(草 24)の 浅草雷門 停留所 から徒歩 5 分
- 都営バス(草 42-3)の 浅草雷門 停留所 から徒歩 5 分
- 都営バス(草 64)の 浅草雷門 停留所 から徒歩 5 分
- 都営バス(草 64)の 二天門 停留所 から徒歩 1 分
- 都営バス(上 26)の 浅草二丁目 停留所 から徒歩 2 分
- 都営バス(都 08)の 浅草二丁目 停留所 から徒歩 2 分
二天門 停留所は浅草神社の横、浅草二丁目 停留所は浅草寺の裏にあります。また、雷門 停留所は浅草文化観光センターの横にあります。
公衆トイレの有無
- なし(隣接する浅草寺に公衆トイレがあります)